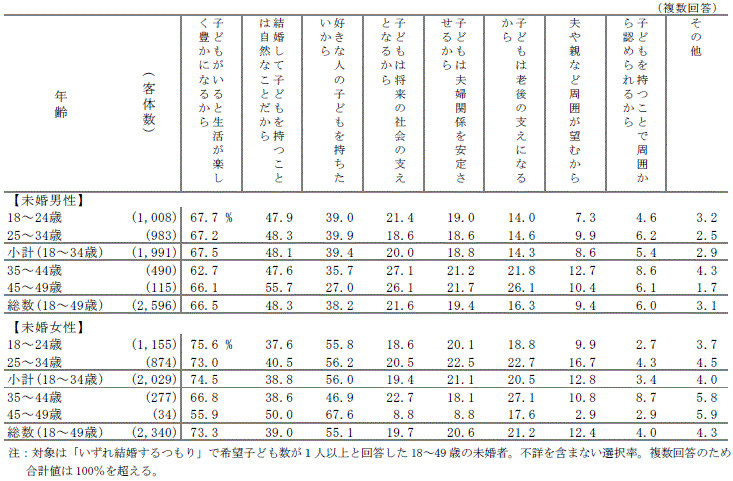反出生主義——生まれない方が/産まない方がよいという思想
※WIXはゴミなのでPC版で見ないとレイアウトが崩れる
決して生まれてしまわないことが最善なのだ。だがもし私たちが日の目を見なければならないのなら、次善は私たちがきたところにすぐに戻ることだ
ソフォクレス(あるいはエウリピデスかアイスキュロスか、ようするに古代ギリシャ三大悲劇作家の誰かしら)はかつてこんなことを言った。
反出生主義(はんしゅっしょうしゅぎ、Anti-natalism)は突き詰めて言えば、この格言を体現し、実践する思想だ。当然そこでは、新たな生命を授かること——つまり子をもうけることは否定されるし、論者によっては、人類ひいてはすべての意識ある生命は明日すぐにとは言わないまでも、穏やかに滅びていく方が倫理的に良いとする、アヴェンジャーズのサノス的なことを吹かすこともある。
一見すると荒唐無稽な戯言で、実際Twitterの検索窓に「反出生主義」と入れると結構な確率でメンヘラちゃんのツイートがひっかかる。他方で、これを真剣に考えている人々も一定数おり、例えば「現代思想」2019年11月号では反出生主義特集が組まれ、気鋭の哲学者や倫理学者、フェミニストたちが熱く論をぶつけ合っている。また文学に目を移せば、生殖倫理を根源的に問うた『夏物語』(川上未映子著、後で詳しく取り上げる)が7月に発刊され、新聞の書評欄を中心に大きな反響を呼んだ[1]。反出生主義は、近年になってやっと公的空間にて議論される土壌が醸成されてきたトピックであると言えるだろう。
本稿ではデイヴィッド・ベネターの提示する反出生主義を軸として展開していくが、彼の主張は私が見たところ、かなりの論理的強度があり、一つの命法として向き合う価値は十分にある。そういった哲学的地平の話は横に置いておくとしても、全ての人にとって生命が所与である以上、反出生主義は知っておくだけでも(実践者とならなくても)有益な思想であるよう私は思う。
私たちの暮らす社会では、新たな生命を授かることは無批判に良いこととされがちで、その正当性が問われることは通常滅多にない。しかしながら(どういう思想を持っていようが)、元来一つの生命を誕生させるということには無限の責任と不可避の暴力が生じる。したがって手放しに、何も考えずに、無批判に、新たな命の誕生を祝福することは本来あってはならないことなのだ。そう考えると反出生主義とは、出生を無条件に肯定する社会における劇薬ともいえる。この劇薬によって、逆説的に生命の重さがクリアに理解できるようになるし、また子を持つ人々にとってみればその道義的責任について自覚的になることができる。これほどまでに生命と真摯に向き合う誠実な思想というものもなかなかない。
私自身は(もうすぐ結婚するけど)、明確に反出生主義の立場にいるため、以下の論考で徹底的に出生主義と子を産むことを批判していくが、別に他人に子を持たないことを強制するわけではない。というかそんな権利、私は1ミリも持っていない。また「とっとと死ね!」と言っているわけでもない。意外に思われるかもしれないが反出生主義の多くの論者は自殺を推奨しない。後に詳細は論じるが、議論をちょこっと先取りしておくと、「今ある生命がなくなること」と「そもそも誕生しないこと」は決定的に違う。前者が生きた痕跡が必然的にこの世界のどこかに残り、死というおそらく最大の苦痛を味わうことになるのに対し、後者においてはそもそも生の残骸と死への恐怖は、はなっから存在しないのである。0とnullの違いともいえるかもしれない。
前書きというか能書きの最後に以下の議論の見取り図を示しておこう。まず哲学的な議論に踏み込む前に、日常を暮らす市井の人が抱く「素朴な」出生主義を批判し、これらがいかに謬計に基づいているか示しておこう。想定しうる出生の「素朴な」倫理的正当性は、おそらくここであらかた排除される。次に政治、宗教と近代哲学の中における反出生主義をさくっと解説する。こうして議論の土台を固めた上で、いよいよ本格的な倫理学的論考に入る。ここでは現在、反出生主義を牽引している論者デイヴィッド・ベネターの主張について深く検討する。あわせて彼の主張に対する主な批判と、その批判の多くがうまくいっていないことも明らかにする。そして結部でベネターの主張に対する私なりの批判を加えて終わろうと思う。
一応、読者のこと(まったくもって謎だが、Wixのアナリティクスによれば、本サイトは月にだいたい300~500くらいアクセスがあって、本当に誰が読んでんだよって感じだけど)を考えて、各々の関心に合わせた読み方についても書いとく。前提として各部ごと単体で見てもお話はなんとなくわかる構成にしたので、どこから読もうが無問題なのだが、まずあなたが「素朴な」出生主義者、あるいはそもそも出生・反出生とかまったく考えず、生命に対して鈍感に生きてきたのであれば、1.「素朴な」出生主義とその批判に目を通してほしい。ぶっちゃけここが一番伝えたいとこなので、それ以下は興味があればって感じだが、2.様々な領域における(反)出生主義では、哲学的、宗教的、政治的視点から、今日的な反出生主義の前景を素描するので、関心があればそれなりに面白く読めると思う。3.ベネターの反出生主義に至るとテクニカルタームもけっこう出てくるので、学術的な文章を読む訓練を受けてきた人ないし受けようと思っている人以外にはおすすめできないかもしれない(と言っても、ベネターの論はとても簡単なものなので完全に理解不能ともならないとも思う)。ラストの4.川上未映子『夏物語』と実存の問題では、哲学とか政治とか抜きにして私たち一人ひとりが、子を授かるというライフイベントにどう向き合っていくか——つまり実存の問題としてどう向き合うかが、論じられる。実存的観点はベネターの主張からすっぽり抜け落ちているものであるため、同時に彼への批判という体裁もとることになる。個人的にはここが一番の熱量を持って書く予定だ。
INDEX
子を持つべき理由①:親の人間的成長、老後の面倒を見てもらうなど
子を持つべき理由②:人間社会の存続・維持のため
子を持つべき理由③:子自身の幸せのため=幸せな人を誕生させることは善
子を持つべき理由④:子を授かることは個人の権利(だから外野がガチャガチャ抜かすな)
2-1.政治
2-2.宗教(というか仏教)
2-3.哲学
3-1.基本的非対称性
3-2.個別的な4つの非対称性
3-3.ベネターへの批判とその応答
4-1.夏物語の第1部
4-2.夏物語の第2部
1.「素朴な」出生主義とその批判
人生は地獄よりも地獄的である
芥川龍之介
冒頭に書いたように子を授かることは、私たちの社会では無条件によいこととされがちだ。さらにいうと、子を持たない選択をする人、もしくは身体的問題、性的趣向、社会・経済的な都合などなどの理由から子を「持てない」人に対して、無言あるいは有言の圧力がかかっていることも周知の事実だろう。杉田水脈とかいう似非ナショナリストのクソゲボ政治家が、セクシャル・マイノリティを指して「生産性がない」(杉田 2018)とか抜かしやがった話も記憶に新しい。ちなみに国家などの公の権力が生命の誕生に対し介入していく事態を、ミシェル・フーコー御大は類まれなる慧眼から「生権力」として分析しているが、話がそれるので置いておく(後で余力あれば解説するかもしれない)。ともかく、子を持つことは良いことであり、特別な事情のない限り子を持たないことは悪なのであるという規範が広く共有されており、ひとたび子を持たないという選択をすれば、批判に曝される可能性があるというのが私たちの暮らす社会なのである。
ここではその際、「素朴な」出生主義の側に立つ人々が暗に承認しているか、大々的に掲げる出生推奨の理由を箇条書きで列挙した上で徹底的に叩く。通常良いこととされる出生への批判は多くの人の直観に反しているが故に、強い反発の感情を喚起するかもしれない。しかし哲学的思考の第一歩はいつでも、自明視される観念に一石投じることから始まる。
子を持つべき理由①:親の人間的成長、老後の面倒を見てもらうなど
これらがいかに利己的で自己本位的な都合であるか、ということはそんなに深く考察しなくてもわかるだろう。まったくもって子のことを考えていない、恐るべき自己中心主義である。しかし、人口問題研究所の2015年の調査[2]によれば、子をもうける理由として、こうした自己本位的な理由を掲げる人は多い。というか圧倒的マジョリティだ。以下の表を見てもらえばわかるが、例えば「子は老後の支え」とする人は、男性全体で約16%、女性全体で約21%。「生活が豊かになる」と答えた人に至っては男性で約7割、女性では7割超にも及ぶ。
これらの理由がなぜ倫理的に悪なのか、ということは親の利己ということに尽きるのだが、もうちょっと深く掘り下げてみよう。
まず当たり前のことだが、子は他者である。親の一部でもないし、人間的成長の糧でもない。一つの自律した人格を持つ「個」だ。子は確かに成長過程にあれば未熟であり、親の庇護のもと、経済的にも社会的にも生活しなければならない。しかし、だからといって将来的に親の面倒を見る義理なんて砂かけらのひとつもないのである。ここで「育ててやったから面倒を見るのは当たり前だ」と思う方もいるかもしれない。しかし、そもそも頼んでもないのに勝手に産んだのは親だ。だから、むしろ「勝手に産んでしまったのだから全面的に面倒を見るのは当たり前だ」が正しい。「産んだ責任」と「育てる義務」がまず相殺され、初めて親が子に対する借金を返済するのである。これでトントン。あとは子の自由だ。
「生活が豊かになる」という理由についても同様だ。親の「生活が豊かになる」ために子を存在させるなんて、愛玩動物かなにかと勘違いしているのではないか(ちなみに反出生主義界隈においてペットを持つことにも否定的見解を示す論者は多い)。
思うにこれら主張は、子を完全に客体化ないし半ば物象化している。すなわち子を道具やモノとして見なすきらいがある。理性と意識を有する一人の人間をモノとしてみなすことの暴力性。こうした理由のもと生まれた子は、後の人生がどれだけ幸福に満ちたものであろうとも、出生が親の「暴力」に依るものだったというただ一点において、紛れもなく不幸な生であるといえる。
子を持つべき理由②:人間社会の存続・維持のため
2つ目の理由もおそらく多くの「素朴な」出生主義者が抱く観念だろう。実際、新たな世代が生まれなければ、遠い未来に私たち人類は確定して滅びるだろうし、あるいはもっと近い未来において社会保障などの公的サービスを維持できなくなることも想像に難くない。とりわけ少子高齢化社会の日本に生きる私たちは、後者の理由から反出生主義に反対したくなる。しかしながら、これらの理由も倫理に反している。主に以下の3つの反駁がありえる。
まず1点目は、次世代をマスにおける駒としてしか見なしていない点である。これは先に述べたのと同じ物象化の論点から批判される。確かに社会を担う次世代がいなければ我々は滅びるが、他方で「社会を担う次世代」が主体として経験する生についてまったく考慮されていない。その生は辛く、苦痛に満ちたものかもしれない。にもかかわらず、人間社会の存続という抽象的な大義のために生み落とされることは、明らかに暴力性を孕んでいる。繰り返しになるが子は社会の駒ではない。一人の人間である。
2点目は、そもそも人間社会は有限である、という反論だ。次世代が生まれようが生まれまいが、超長期的に見れば人間はいずれ必ず滅びる。宇宙的な視座からすると、次世代を誕生させるということは、その滅びる瞬間(おそらくかなりの苦痛であると予想される)を経験することになるかもしれない世代を生産し続けていくことに他ならない。例えるならババ抜きのババを次へ次へと回し続けている状態、あるいはいずれ爆発する爆弾をパスし続けている状態といえる。楽観的な出生主義者の中には「いやいやそんな宇宙的な話想像できねーしw」と思われる人もいるかもしれない。ではもっとアクチュアルな議論に落とし込んでみよう。
一般に子を誕生させる異性愛者のカップルは2人からなる。ごくごく自明のことだが、意外にも多くの人が気づかない事実を示しておくと、2人のカップルが1人の子どもしか生まなかった場合、少子化は進む。2人の旧世代に対し、1人しか新世代が生まれないから当然だ。2人産んでやっとイーブン。3人目で初めて少子化を防げる。ということはつまり、出生主義の立場に立っていても、1人しか子を授からないのであれば、ラディカルな反出生主義が推す漸進的な「人類滅亡」のシナリオに否が応でも加担していることになる。そして現状、合計特殊出生率は2を大きく割り込んでいる[3]ため、「子を産むとしても1人まで」という世帯が圧倒的に多いことがわかる。換言すれば、少なくとも我が国において、大多数のカップルが「人間社会の滅亡を確定的に推進している」にも関わらず、滅亡の瞬間に立ち会う世代(ババを引く世代)を生産し続けているという非常に歪な構造があることがわかる。
「人間社会の存続」という理由に対する3点目の反論は、より根本的で、かなり説得性の高いものだ。これを考えるにあたって、そもそも人間社会の存続とはなんぞや、ということをざっくりと整理したい。それは例えば経済システムを縮小させることなく・絶え間なく回し続けることかもしれないし、あるいは既存文化の形を変えて再生産していくことかもしれない。もっと卑近なところでいえば、自分の血が流れる一族を存続させることでもあり、自分の所属する共同体を維持することでもあるかもしれない。
と考えると、一つ抜け落ちている観点があることに気づく。すなわち「社会の存続に寄与できない人々」の存在である。あえて具体的にいえば、知的に重度の障害がある人は、おそらく先に挙げた具体的な社会存続のプランにほとんど貢献することはできないだろう。
「社会の存続」という視点は、暗黙裡に(この言葉は嫌いだが)生産性という尺度から生命の価値を評価している。冒頭に出てきた杉田水脈が「生産性」という言葉を使っているのも偶然の符合ではない。これはナチスや、記憶に新しい「やまゆり園事件」の犯人が掲げた思想、いわゆる優生主義にほとんどあと一歩の距離まで接近している。「社会の存続に寄与しない者は生きるに/生まれるに値しない」と。
新たな誕生を社会存続のためとする出生主義者は、例えば出生前診断で我が子に重度の身体・知的障害があるとわかれば——社会を存続する能力がないとわかれば、本当に中絶を正当化するのであろうか。この主張に倫理的妥当性があるとは私には到底思えない。
なお反出生主義には、優生主義に対するカウンターとしての側面もある[4]。優生主義が価値ある生命と、そうでない生命の選別をするのに対し、反出生主義はすべての生命に等しく価値を見出さないためだ。毒をもって毒を制す感が強いが、ともあれ反出生主義の立場をとれば優生主義を真っ向から否定できる。
子を持つべき理由③:子自身の幸せのため=幸せな人を誕生させることは善
生は幸福に満ちており、したがって子を産むことは幸福な人を誕生させることになるため肯定される、というのが「素朴な」出生主義が抱く3つめの理由だ。この主張はそれなりに強力であり、議論の水準は陳腐な言い方をすれば「幸福論」という哲学的な地平に引き上げられる。これには以下の2つの応答が考えられる。
後で取り上げるベネターは人間の幸福を否定するために、1章分まるまる使って「誰の生であってももれなく苦しみに満ちている」ということを仔細に論証している。そもそも生が幸福であるという前提を崩してしまえば、主張が成り立たなくなるというわけだ。しかしながら、彼の論はいささか拙速な内容で説得性に欠ける。ベネターはポリアンナ効果[5]を前提としたうえで、人々が自身のQOLを不当に高評価していると指摘する。さらに3つの幸福の尺度(快楽説、欲求充足説、客観的リスト説)のいずれを採用しても、人間の生は不幸に満ちていると論証することができると豪語している[Benatar 2006→2017]。しかし、彼がいかに完璧な論理と「客観性」をもって人の生が不幸であると主張したところで、けっきょく人間の幸不幸は当人の主観的な水準によってしか測ることができない。その主観が客観的公準や論理と照合して間違っていると指摘できたとしても、当人が幸せな生を謳歌していると言うのであれば、幸せなのだ。
しかし幸せは主観性に大きく依存する、とするのであれば、むしろそこが問題となってくるのではないか。つまり、親の生が幸せだったとしても、それはあくまでの親が見ている世界での話であって、子の見る世界の話ではない。「私が幸せだから、子も幸せなはずだ」という主観的な推論から、子の誕生を正当化することは不可能なのである。
主観性の問題に加え、もう1つ可能な反論は、存在と非存在の非対称性に基づくものである。この存在/非存在の非対称性という概念はベネターの主張の中核を成すものであり、後に詳細を詳しく検討する必要があるが、簡単にまとめてしまえば「①誕生すること=快/害があること(存在)」と「②誕生しないこと=快/害がないこと(非存在)」は後者の方がよりよい(理由は後述)。さらにここから演繹される非対称性として「親には不幸な子を産まない義務はあるが、幸福な子を産む義務はない」というものがある。この命法はなんら直観に反するものではない。子が幸福な生を送るか、不幸な生を送るかは完全に予期不可能である。いわば博打に近い。すなわち博打に負ける=不幸な生を送る可能性が1%でもある以上、この命法に従って、子の幸せを願うならばそもそもこの世に誕生させないことが、倫理的に正しいことになる。
子を持つべき理由④:子を授かることは個人の権利(だから外野がガチャガチャ抜かすな)
子を授かることは個人の権利(幸福追求権ほか諸々)であるため、そもそも反出生みたいな極端な思想を掲げること自体が道徳的に間違っているし、それを押しつけてくるのもおかしい。ついでにいうとうざったい。こうした主張は一見するともっともらしい。冒頭に書いた通り、私自身も他者に強制することには反対する穏当な反出生主義者なので、部分的には頷けるところもある。他方で、反論しようと思ったらいくらでもできるのも事実だ。
まず子作りは個人の権利というが、行為の結果として新たな権利主体(つまり子ども)を存在させることになるため、「個人の」という表現には疑義が生じる。以下の例を考えてみよう。
子作りは、欲しいものを公平な取引に基づいて手に入れるといった経済システム上の獲得プロセスとは決定的に異なっている。
経済的な獲得:Aさん(権利主体)が、財(権利の向かう対象)を入手
子作りにおける獲得:Aさん(権利主体)が、子(権利の向かう対象かつ新たな権利主体)を入手
上記の2種の獲得間には明確に非対称性があるのだが、いまいちピンとこないかもしれない。では次のようなケースを想定してみてはどうだろうか。新たな権利主体である子が、将来的に何らかの理由から反出生主義に目覚め、「生まれないで済んだ権利(a)」を事後的に行使する場合、親の子作りの権利は、子の権利(a)を明らかに侵害していることになる。よって個人の権利訴える子作りは不当なものとして棄却される。
子が自分を産んだことで親に文句つけるなんて、絵空事に感じられるかもしれない。しかし、驚くべきことに実際の事例である。2019年2月に、インドに住むラファエル・サミュエル氏は、同意なしに自分を産んだことを不服として、自身の両親を告訴した[6]。大変興味深い話で今後に注目だが、ここでいいたいことは要するに親の権利は子の権利を十分に侵害し得るので、子作りは「親個人の」権利には回収しきれない、ということだ。
子作りを個人の権利だとする主張に、もう一つ別角度から反論しておく。
常識的に考えて、子の虐待を親の権利だとする主張は明らかに間違っている。すぐさま家庭の外部が介入するべきだし、実際、わが国では児童福祉法第25条によって、虐待に気づいた第三者には通告義務が生じる。
反出生主義は子を産むことを虐待と同程度かそれ以上の暴力と見なす。つまり子作りが暴力であると倫理的に明示できるのであれば、第三者にはそれを止める義務が発生することになる。したがって子作りは個人の権利だから外部が口を出すな、という主張は、ちょうど虐待する親がそうするように、子に対する暴力を私秘的領域に覆い隠そうとする点で、倫理に反していると結論付けられる。
2.様々な領域における(反)出生主義
きみは人生を、存在しないという祝福された平穏を破る無駄な物語だとみなすかもしれない
アルトゥール・ショーペンハウアー
想定される「素朴な」出生主義者が抱く正当化の理由はだいたいこのくらいものだろう。自然の摂理論(子を授かることは生命の至上目的である)も取り上げようか迷ったが、ほとんど検討する価値のない話なのでやめた。これを大マジに言う人がいれば、自然の掟に基づいて生殖する能力のない人々を排除する差別主義者だし、役に立たない生命を淘汰されてもよいとする優生主義者でもあるので、近寄らない方がよいだろう。勝手に動物レベルの生を謳歌してください、って感じだ。
さてここからは、政治、宗教、哲学のそれぞれの領域で、出生主義ないし反出生主義がどのように扱われてきたか、ということをざっくりとまとめる。ぶっちゃけ全体の議論に厚みをもたせるためだけに加筆した節なので、すっ飛ばして次のベネターの節を読んでも何の問題もない。
2-1.政治
当たり前と言えば当たり前すぎる話だが、国家側から見れば自国民の増加は、例外的状態を除けば、富国的観点から基本的には歓迎すべきことだ。少子高齢化社会の日本を生きる我々が日々見聞きしているように、今日では人口増を目的とした様々な施策が実施されている。
しかし、これはあくまで人口減少に傾いている国家においての話であり、世界規模で見るとむしろ人口の過剰な増加に頭を悩ませている国の方が多い。このとき、当該政府は抑制に向けて何らかの方策を打ち出すこともある。よく知られているのは、中国の「一人っ子政策」だろう。「いやいやまた古くて極端な例を(笑)」と思われるかもしれない。しかし一人っ子政策は2015年まで続いていたし、そもそも人口抑制策が近代以降の世界において普遍的に見られる政策である。昨今では2070年に20億人超の人口を抱えると予測されるインドが取り組んでいるし、また意外に知られていないが、高度経済成長期に陰りが見えた直後の日本も、実は人口抑制策を採ったことがある[7]。詳しくはリンク貼っとくので見てくだせえ。
古典経済学ではマルサスが人口抑制について積極的に語っている。彼の主著である『人口論』に登場するよく知られた命題「人口は等比数列的に増加するが、食糧は算術級数的にしか増加しない」(Malthus 1798→2019)から窺えるように、18世紀イギリスにおいても人口増加に伴う食糧危機が切迫した問題だった。しかしマルサスの主張はイノベーションを視野に入れておらず、事実産業革命によって(イギリス料理が不味くなる代償を払いつつも)食糧問題は解決され、今日では人口増加と経済発展が調和的に両立することが判明している。
さて、これら人口抑制策は反出生主義思想に基づいているといえるだろうか。答えはおそらくノーだ。反出生主義は子どもの立場から出生を否定するのに対し、抑制策は国家の合目的性の立場から出生をコントールしようとしている点で一線を画している。確かにイギリスのANP(The Anti Natalism Party)[8]みたいなラディカルなやべー反出生主義的政治団体もいるにはいるが決して大衆の支持を獲得しているわけではない。子どもを産むことは暴力だとか、人生は苦痛に満ちているとか、そういった思想に基づいて大規模な政策が展開されたことはおそらく有史以来ない。したがって人口抑制策を反出生主義のスキーマから理解するのは現状難しいと言わざるを得ない。
ここで次の宗教の話に移ってもよいのだが、ちょうど人口をコントールしようとする権力の話が出ているので、完全に蛇足だがミシェル・フーコーの生権力の議論もついでにちょこっと紹介しておこう。
生権力(Bio-Politic)の議論は後期フーコーの主著、『性の歴史Ⅰ 知への意志』が初出だ。やや長いが明示されている箇所をとりあえず引用してみよう。
君主の権力がそこに象徴されていた死に基づく古き権力は、今や身体の行政管理と生の勘定高い経営によって注意深く覆われてしまった。古典主義の時代における様々な規律制度——学校とか学寮、兵営、工房といったもの——の急速な発展である。同時にまた、政治の実践や経済の考察の場で、出生率、長寿、公衆衛生、住居、移住といった問題が出現する。つまり身体の隷属化と住民の管理を手に入れるための多様かつ技術の爆発的出現である。こうして「生権力」の時代が始まるのだ。(Foucault 1976→1986 p.177)
相変わらずハゲ特有の難解な言い回しが鼻につく。ざっくりまとめると、かつて司法(=死刑)の中にあった権力——すなわち「死に基づく古き権力」は、生命を保障し、繁殖させることにウェイトを置く「生権力」に変容したということだ。本当は生権力には規律と人口調整という2つの極があるという話もしなければならないが、そもそもフーコーは本筋ではないのでこの辺りは割愛。
ともかく出生抑制にしろ、出生推奨にしろ、国家が新たな生命の誕生をコントロールとしようとする際、そこには生を管理する生権力が明確に作用しているのだ。
2-2.宗教(というか仏教)
政治の領域における(反)出生主義が比較的あっさり解説できたのに対し、宗教における(反)出生主義は解説すべき論点が滅茶苦茶に多く、議論は広範に及ぶものとなる。そのため、ここでは伝統的宗教のうち、仏教の出生観にのみフォーカスを絞り紹介したいと思う。
仏教はキリスト教でいうところの聖書に相当する唯一的聖典を持たない宗教で、釈迦本人の死生観を探ろうとするとなかなかに手こずる。そこで仏教学者・佐々木閑の勧めに従い[9]、最も古い時代の文字化された経典集成『阿含/ニカーヤ』を手掛かりに釈迦の考えに迫っていきたい。だいたい『阿含』が編纂されたのが紀元前4世紀ぐらいらしいので、その後主流となる大乗仏教の教えについてここでは触れられていないことに注意してほしい。
まず『阿含』に限らず、仏教を理解する上で必須の2つの概念を紹介しよう。日本ではなかば日常語として定着している、輪廻と業(カルマ)である。
多くの仏教経典によれば、我々、生き物は始まりのない無限の過去から存在していて、寿命が来ると死んで別の生へと生まれ変わり、そこで死んでさらなる別の生へと生まれ変わる、という生と死のサイクルを果てしなく繰り返しているという。そこでは終わりのない無限の未来に向かって、同様の生死をひたすら反復している。
このサイクルは限定された5つの領域の中で繰り返される。空間的上位の領域から順に、天国、人、畜生、餓鬼、地獄がそれだ。これを五道と呼ぶ。興味深いことに日常的シーンでも「来世はハエ(ディスり)」とか「君の前々前世から云々」みたいな発話が観察されるが、おおもとを辿ればこの五道のスキーマが我々日本人に刷り込まれているといえよう。この五種の生物界の中をぐるぐるループし続けること、それがすなわち五道輪廻である。
では、そのような生き死にの無限サイクルを引き起こす原動力はなんだろうか。それこそが業(カルマ)に他ならない。業はある種の因果則だが、そこに倫理的法則性が含まれていることに特徴がある。生き物が悪しき欲求にかられて殺生とか窃盗とかよからぬ行為を行うと悪業のエネルギーとなり、どれほど時間が経過しても本人について回る。善行についても同様で、その場合、輪廻の中でいずれ果報が訪れる。こちらも「天国行き」とか「地獄行き」といった表現からうかがえるよう、日常生活の中に広く浸透した思想であるといえるだろう。
ここまではまだ原始宗教時代の古代インドにおける日常的観念である。釈迦の思索は端的にいえば、この業を原動力とした輪廻を「好ましい」と見るか「おぞましい」と見るか、というところを始発点にしている。
釈迦は後者の立場をとる。どんなに善行を積んで、快をもたらす輪廻を生きようとも、そもそもそれは空蝉の虚構であり、生は苦しみに満ちている。いわゆる「一切皆苦」というやつである。永遠にループする輪廻から脱して初めて真の安寧を手に入れることができる。そして輪廻から脱出するためにはその原動力である業から解放されなければならないのだ。つまり「善いことをするぞ」「悪いことをするぞ」といった一切の強い意志作用を否定し、我々が業を生み出さない状態になることこそが初期仏教の至上目的であり、修行とはそうした欲望あるいは煩悩を捨て去るためのトレーニングであるといえよう。輪廻というシステムの停止と涅槃への解脱。それは我々が生命体の本質として具備している希望、欲望を自力で放棄することを意味するのだ。
こうして考えると「生の一切は苦」といった反出生主義の思想と、一切皆苦といった言葉に表出する初期仏教の教えはそれなりに近しいといえるかもしれない。実際、後で登場する消極的功利主義やショーペンハウアーの反出生主義にも影響を与えているとされる。しかしながら、仏教において教説を実践するのはガチガチの修行僧集団(サンガ)に限定され、全ての人が従うべき普遍的な倫理として反出生を提示するベネターらの主張とは一線を画している。仏教的には反出生の教説に従うよう人に勧めることも、一つの我欲として捉えられ、業を生み出してしまうのである。
2-3.哲学
長いながい前置きがようやくおわって、やっと本題である哲学領域における反出生主義について考えることができる。もうだいぶへとへとだが、たぶん分量的にはやっと半分くらい?次節ですでに何度も名前が登場しているデイヴィッド・ベネターの主張を検討するが、その前準備として本節では、近代以降の哲学の中で、反出生主義がどのように扱われてきたか紹介したいと思う。
出生を肯定した論者はメジャーどころに限定しても多くいる。というか戸谷洋志が指摘するように基本的には多くの哲学者は、子どもの誕生を無条件に肯定的に捉え、希望の象徴として語ってきたきらいがある(戸谷 2019)。例えばハンナ・アーレントは初期の主著『全体主義の起源』の中で、出生とは新しい「活動」を始めること、既存の秩序と性質を異にするものを打ち立てることとしたうえで、全体主義に抗う新たな政治的公共性の萌芽を生命の誕生に見ている(Arendt 1951→1971)。また同じくハイデガーの弟子であり、アーレントと生涯を通じて交流したハンナ・ヨナスも代表的な出生主義の哲学者だ。彼女は子どもの合意や福利といった根拠に依らずに、人類全体に対する責任と義務として出生を肯定する(Jonas 2003)。さらに異なる時代では「繁殖性(Fécondité)」という概念を提唱したエマニュエル・レヴィナスや、「出来事(Événement)」の象徴として誕生を論じるジャック・デリダなどの大御所も出生の側に立つ哲学者として紹介されることが多い。
では反出生主義側の主張はどんなものがあるだろうか。ここではベネターとは異なる反出生主義である①消極的功利主義と、ベネターに繋がる②ショーペンハウアーの反出生主義の2つを対照的に検討しよう。
①消極的功利主義
功利主義は良く知られているように「最大多数の最大効用」を目指す哲学・政治学上の立場である。消極的功利主義というのは名前の通りその逆を行くもので、粗くまとめるなら、功利主義が最大多数にとっての善の産出を志向するのに対し、消極的功利主義は最大多数の苦の削減のみが倫理的重要性を持つとする。
三段論法でまとめると、
苦は削減されるべきである
生は苦である
したがって生は削減されるべきである となる。
消極的功利主義の源流をたどっていくと、カール・ポパーが『開かれた社会とその敵』の中で展開した、マルキシズムやそれに基づくファシズム批判に行き着く(おそらくここが初出)。ポパーによればシジウィクなどの古典的功利主義が掲げる最大幸福の原則は、独裁者の甘言に利用されてきた歴史があるため、より控えめで現実的な原則と置換される必要があるという(Popper 1945→1963=1973)。
消極的功利主義はこのように共産主義的独裁に対するアンチテーゼの文脈で登場したわけだが、反出生主義と結びつくようになったのは比較的最近で、ヘルマン・ベターみたいな自然権論的リバタリアンなどが積極的に議論を展開している(らしい)。ベターの主張は功利の非対称性(幸福な子を誕生させる義務はないが、不幸な子を誕生させない義務はある)に訴えている点で、ベネターと共通している部分もあるが、その帰結においては決定的に異なっている。
先に述べたように消極的功利主義は苦の最小化を目指す。この最小化は、苦痛を感じうる存在がそもそも生み出されないとか、苦痛を感じうる存在がすべて痛みなしに安楽死することによっても達成される。それゆえ消極的功利主義は、いま述べたことのいずれかを行為者が実現することを含意してしまう。一方でベネターは、ひとびとが生きる権利を平等に持つことを認め、死それ自体を悪だと考える。 また(後に吟味するが)すでに存在している人からよきもの(この場合では生命)を奪う行為を不正と見なしている。
つまり「さっさと死ね!」という消極的功利主義に対し、ベネターの反出生主義は誕生を否定しつつも、能動的な死を決して肯定しない点で決定的に異なっているといえるだろう。
②ショーペンハウアーの反出生主義
ショーペンハウアーの名前は聞いたことがある人も多いだろう。古くは「デカンショ(デカルト・カント・ショーペンハウアー)」などとも言われ、近代哲学を知るうえでマストな人物の1人とされてきた。
ショーペンハウアーの死生観は仏教のそれと極めて近しい。というかそのまんまと言ってもほとんど差し支えないレベルだ。仏教には一切皆苦という言葉があるのは先に触れたが、ショーペンハウアーも主著『意志と表象としての世界』の中で、主体が意慾し続ける限り、生存は必然的に不断の苦を背負っており、「一切の生は苦悩である」(Schopenhauer 1819→2004 p.332)という帰結に至っている。
また主著『意志と表象としての世界』の補論である「生きんとする意志の肯定と否定に関する教説によせる補遺」(長い)にも仏教を感じさせる一節がある。彼は涅槃やヴェーダ教の大熟眠位(magnum sakhepat)を例に挙げた上でこう述べる。
生きんとする意志の否定ということは決して或る実体の絶滅を意味するものではない。それは単に意慾しないというだけの行為なのである。——即ち、これまで意慾してきたその同じものが、最早意慾しなくなるということなのである。ところで我々はこの本質、即ち物自体としての意志を、単に意慾という行為においてのみまたそれ通じてのみ知っているのであるから、それがこの行為を放棄してしまったあとで、なおさらにそれが何であるのか乃至はまた何をやっているのであるかということについては、我々には語ることも理解することもできない。だからしてこの否定は、意慾の現象であるところの我々にとっては、無への移行に他ならないのである。(Schopenhauer 1851→1952 pp.83-84)
この引用部は、前節で見た初期仏教における苦に満ちた生のループ——つまり輪廻の停止と涅槃への解脱の変奏であると受け取ることができるだろう。またここでの意慾の放棄とは、現世における業の放棄のことを意識していると思われる。
ベネターもこうした仏教=ショーペンハウアー流のペシミズムは色濃く継承しており、事実、人生が苦痛に満ちていることを論証する際に想定される楽観主義者からの批判を、ショーペンハウアーの言葉を借りて反論している(Benatar 2006→2017 p.99)。
3.ベネターの反出生主義
たしかに、生誕を災厄と考えるのは不愉快なことだ。生まれることは至上の善であり、最悪事は終末にこそあって、決して生涯の開始点にはないと私たちは教え込まれてきたではないか。だが、真の悪は、私たちの背後にあり、前にあるのではない。
エミール・シオラン
デイヴィッド・ベネターは現在、南アフリカのケープタウン大学で教鞭をふるう哲学者で、『生まれてこないほうが良かった——存在してしまうことの害悪 (2006→2017)』において、これまであまり日の当たることのなかった思想、反出生主義を体系的に論じたことで一躍脚光を浴びた。
ここではベネターが件の『生まれてこないほうが良かった』で展開する主張を簡潔に解説し、その批判についても整理しようと思う。ベネターは論理学寄り(正確には論理実証主義寄り)の分析哲学の手法を用いて、出生あるいは存在がいかに害悪であるか、ということを論じている。彼は論理学くずれの文体を駆使するため、とっつきにくい印象を受けるが、その実、極めて単純な話なので肩の力を抜いて気軽に読んで欲しい。なお『生まれてこないほうがよかった』は訳が生ゴミ以下(院生が訳したのか?Google翻訳の方がもっと頑張りそうなものだ)、もし興味があるならば値段もそんなに変わらない英語版”Better Never to Have Been the Harm of Coming into Exitance”の購入をおすすめします(私は両方買う羽目になりました)。
3⁻1.基本的非対称性
ベネターが出生に反対する論拠は次の2つがある。①2章を通して展開される「非対称性に基づく議論」と②3章で展開される「生の質(QOL)に基づく議論」がそれだ。これら2つは互いに独立しているため、仮に出生を肯定する立場に立つのであれば、①と②に対して個別的な反論を用意する必要がある。
しかしながら、本稿第1節で論じた通り、②の生の質に基づく議論は仏教=ショーペンハウアー的な「一切皆苦」の思想を継承しているとはいえ、諸手を挙げて賛同できる内容ではない。というがガバガバの穴だらけだ。彼によれば、人々は悪いことよりも良いことを評価し、概ね幸福な人生を送っているという錯覚に陥っているという(Benatar 2006→2017 §:3)。心理学的にはこれをポリアンナ効果と呼び、その効果が人生の実態を覆い隠すヴェールとして機能しているというのが彼の一貫した主張だ。『生まれてこないほうが—』3章において、不当に覆い隠された生がある、という前提のもとに、ベネターはヴェールを剥ぎ取ることに終始しているが、生の善悪を客観的に数値化することができない以上、実質QOLは常に体感QOLより低く、また生まれてくることは常に悪であるという誕生害悪説を受け容れるには、個人の実感、つまり主観的な感覚に依るしかない。だが主観的にめちゃくちゃ幸福で充足した生を謳歌している人に対して、「君は自分のQOLを不当に高評価している!君は不幸だ!」と言ったところで、歯牙にも掛けられないだろう。ベネター「生の質に基づく議論」ははっきり言ってほとんど検討する価値がない。
したがって、ここでは2章で展開される①「非対称性に基づく議論」の方を中心的に取り上げる。多くの哲学者が補強する主張を提示したり、あるいは強く反論したりしていることからもわかるよう、『生まれてこないほうが—』の肝は非対称性議論にある。
非対称性に基づく議論の目的は、「生まれてくることは当人にとって常に悪である」という結論を示すことにある。そのことを示すために、ベネターは、人が生まれてくる(存在する)場合と、生まれてこない場合(存在しない場合)の福利を比較する。ベネターによれば、こうした比較によって、生まれてこない場合の方が生まれてくる場合に比べて常によりよいと言える。それゆえ、生まれることは当人にとって常に(生まれないことよりも)悪であることが導かれる。これが議論全体の骨格である。
この議論で重要なのは、「福利について比較したときに、生まれてこない場合のほうが、生まれてくる場合に比べて常により良いといえる」ということである。そして、この主張を導く鍵となるのが、快楽と苦痛の間に存在する重要な非対称性である。
ベネターは快楽や苦痛の存在については、次の2つが成り立つと主張する。
(1)苦痛が生じることは、悪いことである。
(2)快楽が生じることは、よいことである。
他方、快楽や苦痛の不在については次の2つが成り立つ。
(3)苦痛が生じないことは、その良さを享受する人がいない場合でもよいことである。
(4)快楽が生じないことは、現に存在する人が快楽を奪われているという場合でないかぎり、悪いことではない。
(3)と(4)は但し書きがあるので、詳しく解説しておくと、まず(3)における「良さを享受する人」とは新たな子どものことだ。生まれてきたかもしれない子どもが存在しなくても、苦痛が生じないことはよいことだ、というのは「不幸な子を誕生させない義務」が多くの人の直観に反さないのと同様に理解できる。(4)は要するに「誰かから奪われた快楽でないかぎり」快楽の不在はよくも悪くもないということだ。これも簡単な話で、そもそも快楽を経験する主体が存在しないならば、快楽が剥奪されようが誰の不利益にもならない。
さて存在と不在が対称構造とするならば、(1)と(2)の間に成り立つ対称性は、(3)(4)間にも成り立つはずである。しかし、実際はそうなっておらず、(3)が「よいこと」であるのに対して(4)は「悪いことではない」となっている。この(3)と(4)の間に存在する非対称性こそが、ベネターが重視する構造であり、『生まれてこないほうが—』の議論の根幹である。
ちょっとわかりにくいかもしれないので、ベネターがよく使う図を用いて解説しよう。
この図の1~4は先の(1)~(4)に対応している。AはXさんが存在した場合=生まれた場合のシナリオ、BはXさんが存在しなかった=生まれなかった場合のシナリオだ。ベネターは、この図を与えた上で、Xにとって生まれることと、生まれないことのどちらがよりよいかを決めるためには、この表の(1)と(3)を比べ、さらに(2)と(4)を比べるべきだと論じる。つまり、苦痛と快楽それぞれについて、生まれた場合と生まれない場合の福利を比べるわけである。まず、(1)と(3)を比べるならば、どう考えても苦痛が生じない(3)の方が——つまり存在しない方がよりよい。では、(2)と(4)についてはどうだろうか。この場合にはXが生まれて快楽を得ることはよいことだが、それは、Xが生まれずに快楽を得ていない場合よりもよりよい、とは言えない。なぜなら、Xが生まれてこなかった場合の快楽の不在は、(可能存在者としての)Xにとって別に悪くないからである。これらを総括すると、(1)-(3)苦痛について比べた場合は、苦痛がないことはよいことであるため、生まれないことが勝る。(2)-(4)快楽について比べた場合には、快楽がないことは悪いこととはいえないため、生まれることが生まれないことに勝ることはない。
えっ?まだわかりにくい?困った。じゃあもっと簡単に数値化して考えてみよう(このやり方はある角度からの哲学的批判を許すことになるためあまり得策じゃないのだが)。
【シナリオA=Xが存在】
(1) 苦痛の存在 悪い -1ポイント
(2) 快楽の存在 良い +1ポイント
合計0ポイント
【シナリオB=Xが不在】
(1) 苦痛の不在 良い +1ポイント
(2) 快楽の不在 悪いとは言えない ±0ポイント
合計1ポイント
Aが0ポイントに対し、Bは1ポイントなので、A<B(シナリオB「不在」がシナリオA「存在」よりよい)。したがって産むことより産まないことの方が、存在することより存在しないことの方がよりよい。以上。
たぶんここまで噛み砕けば理解してもらえると思う。議論をまとめると、存在と不在の間には、快楽と苦痛をめぐる重要な非対称性が存在する。快楽の存在は確かによいといえるが、(それが誰かから剥奪したものでないかぎり)快楽の不在に勝っているわけではない。この非対称性に基づき、非出生は出生に勝る。
3⁻2.個別的な4つの非対称性
ベネターは上述の存在と不在の基本的非対称性から以下の4つの個別的な非対称性が導出できると考える。
①生殖に関する義務の非対称性
苦痛を被る人々を避けるのは義務であるが、幸福な人々を存在させる義務はない
→不幸な子を産まない義務はあるが、幸福な子を産む義務はない
②生殖の理由に関する非対称性
子をもつための理由として、その人が持っている子どもがそれによって益されるだろうからというのはおかしいことだが、子どもを存在させることを避ける根拠として、存在するかもしれない子どもの利害を引き合いに出すのはおかしいことではない
→子どもを産むことが当の子どもにとって利益であると考えるのはおかしいが、子どもを産むことが当の子どもを苦しめることになると考えるのはおかしいことではない
③生殖の後悔に関する非対称性
人々を存在させることと同じく人々を存在させないことは悔やまれうる。けれども私たちの選択次第で存在する人のためとなると、人を存在させることだけが悔やまれうるのだ。
→不幸な子を存在させたことは後悔するが、幸福な子を存在させなかったことは後悔しない
④遠くで苦しんでいる人と、どこにもいない幸福な人に関する非対称性
苦痛に彩られた人生を生きている異国の住民のことを想像すると心を痛めるが、ある無人島の話を耳にして、もし存在していたらその島に住んでいた可能存在者としての誰かの幸福が存在しないことに対しては悲しみを覚えない。
ベネターによれば前節の基本的非対称性を認めるならば、これらすべての非対称性を説明することができる。例えば①の生殖の義務に関する非対称性は次のように説明される。私たちが苦しむ子どもをつくるべきではないのは、苦痛が生じることが悪く、苦痛が存在しことがよいことだからである。他方で、私たちが幸福な子どもをつくる義務を負わないのは、幸福な人が存在し快楽を得ることはよいことだが、幸福な人が存在しないことはそれに比べて悪いことではないからである。同じような説明は②‐④にも与えることができる。したがって、ベネターは基本的非対称性が4つの非対称性の最善の説明になっており、それゆえ基本的非対称性を受け容れるべきだと結論する。
3⁻3.ベネターへの批判と応答
ベネターの非対称性に対する批判は多くあるが、大きく[ⅰ]基本的非対称性がそもそも成り立たないとする反論、[ⅱ]4つの非対称性は認めるが、基本的非対称性よりうまい説明があるとする反論の2つに分けることができる。当然、無数にある反論すべてをここでとりあげるのは無理なので、[ⅰ]方向の批判からデイヴィッド・スパーレットのものを、[ⅱ]方向の批判からデイヴィッド・ブーニンのものをピックアップすることにする(みんなファーストネームがデイヴィッドだ)。
[ⅰ]スパーレットからの批判
スパーレットは個別的非対称性が広く受け入れられるとするベネターに対して懐疑的だ。例えば彼は「生殖に関する義務の非対称性」が、「実り豊かに繁栄すべし」といった神の命令に従う宗教的な人々や、ある国家や民族の存続を考えて子作りしなければならないとするナショナリストには受け入れ難い命題であるとして批判する(Superrett 2018)。こうした包括的教説を信仰するのであれば、子を産む義務が外在的に生じるというわけである。
しかしこれはベネターが応答しているように「ふざけた反論」だ(Benatar 2019 §:2)。ベネターはあくまで子の福利の観点から反出生主義を唱えている。それに対しスパーレットの主張は包括的教説に従う人々の観点から義務を擁護している。彼らがそうした義務に従うのは、国家や信仰する神のためであって、子孫のためではない。したがって、スパーレットの批判は同じ土俵にあるとは言えず、そもそも批判としての体を成していない。
またスパーレットの批判は基本的非対称性にも及ぶ。ベネターの非対称性の図は先ほど見た通りだが、スパーレットは快楽と苦痛は範例として不十分であり、それ以外の害と利という対立図式が導入されるべきであると主張する。それを踏まえると、シナリオAに「(5)価値のある人生の存在=良い」、シナリオBに「(6)価値のある人生の不在=悪い」という一文が追加されることになるという(Superrett 2018)。
これに対しベネターは害/利への範例の移行には、例の図に余計な一文を書き足す必要などなく、快楽/苦痛の部分を害/利に書き換えるだけで済むと反論している。このやり方に従えば、スパーレットが望む害/利への範例に移行したところで、非対称性は変わらず存在するため、けっきょく出生は否定され、存在は害悪のままである。
[ⅱ]ブーニンからの批判
ブーニンは基本的非対称性を、よりよい説明によって暫定的に代替させることによって、(当人のQOLが十分に保証できる場合には)新たな生命を誕生させることは道徳的に容認されるという見解を導き出す。彼の解決策は相対的対称性原理と実在人物原理の組み合わせからなる。
[相対的対称性原理]
(1)苦の存在は内在的に悪い
(2)快の存在は内在的に良い
(3)苦の不在は、以下のどちらかの場合にのみ、苦の存在よりも良い
(a)苦の不在が、その人の利益になる実在の人が存在する場合
(b)苦の存在がある人の存在を要請し、その人は苦の存在に要請されない限りは存在しないのだが、苦の不在が当人にとっての潜在的な利益にとってよりよい場合
(4)快の不在は、以下のどちらかの場合にのみ、快の存在よりも悪い
(a)快の存在がその人の利益になる実在の人が存在する場合
(b)快の不在がある人の不在を要請するが、その人は快の不在に不在を要請されない限りは存在し、また快の存在が当人にとっての潜在的な利益にとってよりよい場合
[実在人物原理]
二つの選択肢のどちらかを選ぶ際、次のような選択をするのは一応、間違いである。その選択に基づいて行動すれば。あなたの行動のせいである人にとっての事態がより悪くなってしまう、そんな実在の人がいることになってしまう選択である。
相変わらず訳がゴミなので(相対的対称性原理に関しては日本語として成立しているか怪しいレベルだ)、ちょっと噛み砕いた上で敷衍する。
先に述べたようにブーニンは基本的非対称性を相対的対称性原理に置換することで、どんな生が始めるに値するか、どんな生ならば創り出しても害にならないか、ということを説明しようと試みている。その際、ポイントとなるのは相対的対称性原理(3)の(b)と、(4)の(b)だ。
(3)苦の不在が、苦の存在よりも良い
と言えるためには次の2つの要件のどちらかを満たす必要がある。つまり
(a)実在人物にとっての苦の不在である場合
(b)未実在人物にとって、その人の人生がそもそも始めるに値しないものであった場合
一方で、
(4)快の不在が、快の存在よりも悪い
と言えるのも、次の2要件のどちらかを満たす場合である。
(a)実在人物にとっての快の存在である場合
(b)未実在人物にとって、その人の人生が始めるに値するものであった場合
このうち両者の(a)は小難しい言い回しだが、私たち実在人物にとって苦の不在と快の存在は良いことだから自明である。問題は(b)だ。ブーニンは「始めるに値しない生」「始めるに値する生」という但し書きを加えることで、呪われたカップルが(人生においてたった100の快と、100万の苦が存在する)呪われた子どもを産むことは否定しつつも、祝福されたカップルによる(人生において100万の快と、たった100の苦しか存在しない)祝福された子どもの誕生は容認する。換言すれば(4)の(b)に従い、QOLが十分に保証される場合であれば、子をもうけることは正当であるという帰結が導出される。
ブーニンは自身の説明をベネターの基本的非対称性をより正確に言いなおしたものであると断言するが、ベネターが反論するようにこうした原理の改変はいささか論点先取りである(Benatar 2019)。まず子を誕生が容認されるケースを想定した上で、基本的非対称性を組み替えるというやり方は、結論ありきの方法で、否認されなければならない。
そもそもベネターの主張の肝心なところは、仮に祝福された子どもであったとしても、なお苦の不在が未実在人物の生において享受する快よりもよいと言い得る点にある。同様に実在人物にとっての快の存在が未実在であることよりもよいとは常に言えない。
またブーニンの見解に従えば、確かに個別非対称性「①幸福な子を誕生させる義務はない」は退けることはできる。幸福な子を誕生させる義務はないが、他方で(4)の(b)より幸福な子を誕生させることは正当であると主張できるからだ。しかしながら、他の個別非対称性②-④を否定することはできていない。なぜなら、それら三つの非対称性は、私たちの義務、つまり何をすべきですべきではないかに言及しているわけではないからである。②-④は人々にとって何が良いか悪いかという話であり、ブーニンの義務論的性格な反証からその説明を導き出すことはできない。
本節では、ベネターの基本的非対称性、個別的非対称性、それらに対する批判とベネターからの応答を順に追って見てきた。ベネターの論理は冒頭に書いた通り、完成度が極めて高く安易な反駁は許さない。クリティカルな反論がないわけではないが、「論理で挑む限りにおいて」ベネターの主張を突き崩すことはかなり険しい道のりになるだろう。
しかし、この完璧に見えるロジックから、子をもうけることを肯定する人、出産を切に望む人、すでに子を持ち、時に喜び、時に苦悩しながら子育てに励む人たちの人生を否定して、いかに彼らの考えが誤謬に基づくものか論証し、苦しみの新たな主体である子を産むことがいかに暴力に満ちたものであるか説き伏せることは果たして肯定されうるのだろうか。知的なゲームにおいては、確かに誠実な実践であると言えるかもしれない。
だが、人は論理にのみ従って生きているわけではない。
人間は、完全無欠(に見える)論理を提示すれば、ああそうか、自分が生まれたのは親の暴力によるもので、新たな子をもうけることは暴力の再生産に他ならないのか、と納得できるほど単純ではない。生殖倫理という人生の最大のテーマにおいて、他者や環境と複雑に絡み合う心の営みは、ただ単に強固であるだけの論理によって矯正されるほど単純ではない。
ベネターの仕事は知的誠実さに応えるものであっても、こうした実存的視点を根本的に欠いている。次節では川上未映子が今年の夏に上梓した小説『夏物語』を手掛かりに、生命を授かることはどういった責任が伴うことで、どういった反論がありえるのか、ということに切り込んでいきたい。
4.川上未映子『夏物語』と実存の問題
その赤ん坊は、わたしが初めて会う人だった。思い出のなかにも想像のなかにもどこにもいない、誰にも似ていない、それは、わたしが初めて会う人だった。赤ん坊は全身に声を響かせ、大きな声で泣いていた。どこにいたの、ここにきたのと声にならない声に呼びかけながら、私は胸のうえで泣きつづけている赤ん坊をみつめていた。
川上未映子
前節ではベネターの非同一性問題を軸として、アカデミックな世界における反出生主義の扱いを考えてきた。ベネターの立論は強固で、反論の余地がないように思えた。他方で、前節の終わりに書いた通り、それは論理としての完成度は高くとも、私たち一人ひとりが新たな生命にどう向き合うか、という実存的問いに応答してくれるものではなかった。
本節では川上未映子の『夏物語』の批評もどきを通して、ついでに文体もアカデミック文体から、柔らか文体にモードチェンジして(同じ文章の中で異なる文体を使い分けるのはけっこう高度な技術であると同時にしんどい)、もっと実存に根差した反出生主義について考えていこうと思う。
まずは作者の紹介から始めよう。川上未映子は気鋭の小説家で、2008年には芥川賞を受賞している。読者層は……まぁよくわからんが個人的な印象としては、「本好きアピールをしながら東野圭吾とかのあっさい作品を読んでいる層を心底馬鹿にしている本当に本が好きな層」が読んでるイメージ。あとファンはやっぱり女性が多いんじゃなかろうか。内容的にも。作品は平易な文体ながらも、社会の荒寥を子どもや、貧しい人々、女性といった抑圧された層の目を通して鋭く切り取ったものが多い。
実は著者も川上作品をいっぱい読んでいるわけではないため、あんまり勝手な放言を書くとガチファンから叱られそうだし、この辺で作者紹介は終わりにする。
4-1.夏物語の第1部
『夏物語』は川上の最新作で、いま現在彼女の作品で最も長い[10]。といっても前半部分は2008年の芥川賞受賞作した『乳と卵』の焼き直しで、加筆修正をして話に広がり持たせていって、長編小説に仕立てた、ってな体裁だ。
本作は1部2部に分かれていて、前半(これがさっき書いた『乳と卵』の焼き直し部)では東京に暮らす夏子(主人公)のもとに遊びにやって来た姉の巻子と、その娘緑子の3人による、ある夏の三日間が描かれる。明らかに貧困層でありながらも巻子は豊胸手術を受けたがっており、思春期の緑子は自分の身体が日に日に「女性」になっていくことに対する不安をノートに書き綴っている。そんな感じで前半は女性の身体性がテーマの一つになっているかな。
緑子がノートに綴る独白は、思春期特有の心の揺らぎと鋭利な感性をうまく表現している。長いけどちょっと抜粋してみよう。
もし、わたしに生理がきたら。それから毎月、それがなくなるまで何十年も股から血がでることになって、それはすごいおそろしい。それは自分でとめられず、家にもナプキンはないし、それを考えるとブルーになる。
もしも生理がきてもお母さんにはいうつもりないし、ぜったいに隠して生きていく。だいたい本の中に初潮を迎えた(←迎えるって勝手にきただけやろ)女の子を主人公にした本があって、読んでみたら、そのなかで、これでわたしもいつかお母さんになれるんだわ、感動、みたいな、お母さん、わたしを生んでくれてありがとう、とか、命のリレーありがとう、みたいなシーンがあって、びっくりしすぎて二度見した。
本のなかではみんな生理をよろこんで、にっこにこでお母さんに相談して、お母さんもにっこにこであなたも一人前の女ね、おめでとう、とか。
じっさいにクラスでも家族みんなに報告して、お赤飯たいたとか食べたとかきいたことあるけど、それはすごすぎる。だいたい本に書かれてる生理は、なんかいい感じに書かれすぎてるような気がする。これを読んだ人に、生理をまだしらん人に、生理ってこういうもんやからこう思いなさいよってことのような気がする。
こないだも学校で移動んとき、あれは誰やったか、女に生まれてきたからにはぜったいにいつか子どもを生みたい、と言ってた。たんにあそこから血がでるってことが、女になる、ってことになって、女としていのちを生む、とかでっかい気持ちになれるんはなんでやねん。そして、それがほんまにいいことやってそのまま思えるのは、なんでやろ。わたしはそうは思えんくて、それがこの厭、の原因のような気がしてる。こういう本とかを読まされて、そういうもんやってことに、されてるだけじゃないのか。
わたしは勝手におなかが減ったり、勝手に生理になったりするような体がなんでかここにあって、んでなかに、とじこめられてるって感じる。んで生まれてきたら最後、生きて、ごはんを食べつづけて、お金をかせぎつづけて、生きていかなあかんのは、しんどいことです。お母さんを見ていたら、毎日を働きまくっても毎日しんどく、なんで、と思ってしまう。これいっこだけでも大変なことやのに、そのなかからまたべつの体をだすのは、なんで。そんなことは想像もできひんし、そういうことがほんまにみんな、素晴らしいことやって、自分でちゃんと考えてほんまにそう思ってるんですかね。ひとりでおるとき、これについて考えるとブルーになる。だから、わたしにとっていいことじゃないのはたしかやと思う。
生理がくるってことは受精できるってことで、それは妊娠。妊娠というのは、こんなふうに、食べたり考えたりする人間がふえるということ。そのことを思うと、絶望的な、大げさな気分になってしまう。ぜったいに、子どもなんか生まないとわたしは思う。
(pp.48-50)
さっき思春期特有の心の揺らぎみたいな風に書いた。しかしこれは正確な表現ではないのかもしれない。なぜなら私は女性の思春期を経験したことがないからだ。引用部の緑子の女性性への根源的な嫌悪は、思春期における一過性の感情なのか、あるいは女性がみんな生涯通して思ってんのか、あるいは女性のうちの一部が思ってんのか、私にはどうしたって判別できない。私は男なので、生理も来ないし、胸も膨らまない。さらに言えば、散々ここまで上の節で「子作り」だの「子を産む」だの講釈垂れておきながら、そもそもそれらは私の人生ではどうやっても経験することができない。出産は究極的には、(その人が「女性」とは限らないが[11])子を産める身体を持つ人でしか、主体として経験することはできない。
これはとても大切なことだ。ベネターもショーペンハウアーもシオランもみんな男だ。男が出生を論理的に否定してドヤ顔しても、どうしてもリアリティや身体性が欠如する。だから、いまやA4の22ページ目に突入したこの長い文章にも思考の限界がある。このことは男で反出生主義を訴える人はしっかり自覚しておく必要がある。
4-2.夏物語の第2部
2部は1部で描かれた夏の3日間から約10年後の話。主人公の夏子は40歳手前に念願だった小説家デビューがかなったものの、ヒット作は1つだけ。売れない、書けない作家として、三軒茶屋で細々暮らしている。緑子は成長し大学生で、巻子も四十路で変わらず雇われママを続けている(が、2部ではこの2人は脇役に収まっている)。
2部の主題はなんといっても生殖倫理だ。夏子が酔っ払って書いた黒歴史ポエムノートを見返す場面で、初めて読者はこの小説の真のテーマを知る。
これでええんか 人生は
書くのはうれしい ありがとう人生の
わたしの人生に起こった
素晴らしいできごと
でもわたしはこのままいくんか ひとりでよ
このままずっといくんかまじで
淋しい と書けばほんまで嘘 でもそうじゃない
わたしはこのままひとりでいい
いいけど、わたしは会わんでええんか
わたしはほんまに
わたしは会わんでええんか後悔せんのか
誰ともちがうわたしの子どもに
おまえは会わんで いっていいんか
会わんで このまま
(pp.197-198)
夏子は現在独り身で、お金もない。また特定のパートナーが欲しいわけでもなく、気になる人もいない。むしろセックスに対して強い嫌悪感を持っており、それが理由で人生唯一の恋人と別れたこともある。こうした気持ちが夏子の性嫌悪によるものなのか、あるいは未熟さ故なのか、それともそもそも無性愛者なのかは明確には描写されない。
とにかく「セックスは嫌だが、子どもは欲しい」と漠然と思っている。そんな折に、夏子はテレビでAID(Artificial Insemination by Donner)について知る。AIDというのはフィクションではなく実在する不妊治療で、端的にいえば夫以外の第三者の精子提供を受けて行う人工授精のこと。日本語だと非配偶者人工授精なんてふうにいう。あんまり日本では馴染みのない言葉で、じっさい法整備も追い付いてないらしい。興味があれば各自調べてください[12]。
当然だが、精子は匿名提供のため、AIDによって生まれてきた子は(生みの親より育ての親みたいな話は置いといて)本当の父親を知ることはない。AID自体がまだまだマイナーなため、あまり表立って問題化することはないが、本当の父親を知れないことは人権的にどうなのか、といったことが当事者サイドから度々問われているらしい[13]。
『夏物語』でもそうした悩みを抱える人物が登場する。それが本作唯一の「生身」の男性キャラクター逢沢潤だ。逢沢は父親だと思っていた人物の死を契機に、自分がAIDによって生まれた子どもであるということを知る。彼の境遇と、因循とした価値観を持つ自身の祖母から投げかけられた言葉を思えばある意味AIDの「被害者」ともいえるかもしれない。自分を構成する半分が出所不明であるという、出生に投げかけられる根源的疑念。夏子と逢沢が出会うことで物語は加速していく。
逢沢の他にも2部には魅力的なキャラクターが多く登場する。作者が出生の是非を巡って多声の多層化を目指した[14]と言うように、様々な境遇の女性たちが物語を彩る。貧しいながらも緑子を何とか大学に行かせたシングルマザーの巻子。女で一つで子を育て、仕事をバリバリにこなす編集者の仙川。大学教授の旦那と別れシングルとなるも、売れっ子小説家で、出生を礼賛する遊佐などなど。
主要登場人物である彼女たちが全員シングルマザーであること(ちなみに夏子と巻子の母もシングルだ)。またAIDというセックスが介在しない出産方法がテーマになっていること。これらを踏まえると、本作の主題は生殖倫理の他に、男性性ないし父性の否定というものもあるといえるかもしれない。この辺も突っ込んで読み込んでいけばたぶん楽しいだろうけど、本稿はあくまで反出生主義の話に限定したい。
そこで取り上げたいのが2部後半に登場する善百合子の存在である。善は逢沢と同じくAIDによって誕生したが、幼い時から血のつながらない父親に性的暴行を受け続けてきたという壮絶な過去を背負っている。また彼女はラディカルな反出生主義者だ。
「でも。わたしはすごく単純なことを考えているだけなの。どうしてみんな、こんなことができるんだろうって。どうしてみんな、子どもを生むことができるんだろうって考えているだけなの。どうしてこんな暴力的なことを、みんな笑顔でつづけることができるんだろうって。生まれてきたいなんて一度も思ったこともない存在を、こんな途方もないことに、自分の思いだけで引きずりこむことができるのか、わたしはそれがわからないだけなんだよ。」
(p.433)
これは余談だが(余談でもないが)、文学批評的に捉えると、善が反出生主義者であることの「動機付け」として、身内から性的虐待を受けていた過去を背負わせるのは、卑怯な表現であるように思う。反出生主義の考え方は(現に幸福と言えないまでも不幸な生を送ってきたわけではない私がそうであるように)誰だって抱きうる。凄惨な過去や明らかに不幸な過去は別に必要としないし、特異な思想でもない。だから善をそうした境遇に置いたこと=反出生主義をどこか異質な思想と見なしていること。その一点において読者には川上未映子を批判する権利があると思う。
まぁそれはそれとして、「生まれてくることを肯定したら、もう一日も生きてゆけない」(p.526)と考える善の主張は、自身の出自という最上級の実存の問題を通しているが故に極めて強い。そう考えると「百合子」という名前も極めて象徴的だ[15]。それに対して夏子は「間違っていることだけどそれでも生みたい」という思いからAIDをいつしか熱望するようになる。
「わたしがしようとしていることは、とりかえしのつかないことかもしれません。どうなるのかもわかりません。こんなのは最初から、ぜんぶ間違っていることなのかもしれません。でも、私は」
自分の声がかすかに震えているのがわかった。わたしは小さく息をして、善百合子を見た。
「忘れるよりも、間違うことを選ぼうと思います」
(p.525)
最終的に淡い恋慕を抱いていた逢沢から精子提供を受け、夏子は子を出産し、冒頭に引用した箇所で物語は幕を閉じる。
これを出生賛歌の物語と読むか、反出生主義の物語と読むかは解釈が分かれるだろうし、どちらでも、どちらでもなくても、読み方は自由だ。
夏子の論理ははっきりいって稚拙極まる。そもそも自分で「間違っている」と認めており、出産が孕む暴力を肯定している。それこそベネター的な人(作中では善)が全力で批判しようと思ったら、いくらでもできてしまう。
でもおそらくそうじゃないのだ。論理の話ではないのだ。『夏物語』で問われているのは、ベネターの宇宙的な議論ではなく(それはそれで重要な視点だが)、いま―ここ(here and now)を生きる私たちが、出生という暴力を肯定しながらも、現に今この瞬間も紡がれ続けている未来の世代の物語に対して真摯に向き合えるかどうかだ。
5.おわりに
めちゃくそ久々に文章書いたから疲れた。でも物書くと嫌でも本を読んで、学ばなければならなくなるため、積み本消化するにはもってこいだ。
本当はヨナスとアーレントの思想的連関だとか、デリダやレヴィナスを深堀したかったけど、この辺読みだすと永遠に書き終わらないから割愛。あと3節の政治のところで、クィア理論における反出生主義を取り上げなければならなかったけど(特にエーデルマンとハラウェイの影響力は看過できない)、フェミニズム系の議論は勉強中なのであえて省きました。以上。
[1] https://www.bookbang.jp/review/article/577798
[2] http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/gaiyou15html/NFS15G_html10.html
[3] https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/index.html
[4]現代思想2019年11月号 p,27- 木澤佐登志「生に抗って生きること」
[5] 人間の生において不幸なことよりも幸福なことの方が大きな影響を及ぼすという心理学的効果。詳しくはhttps://ci.nii.ac.jp/naid/110001884923など
[6] https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/02/post-11689.php
[7] https://gendai.ismedia.jp/articles/-/60028?page=2
[8] https://antinatalism.co.uk/
[9] 現代思想2019年11月号 p.154- 佐々木閑「釈迦の死生観」
[10] https://books.bunshun.jp/sp/natsumonogatari
[11] 2008年にトマス・ビーティというトランス「男性」が出産している。詳しくはJanssen 2017 p.11
[12] https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6986
[13] https://toyokeizai.net/articles/-/205944
[14] https://www.tokyo-np.co.jp/article/book/kakuhito/list/CK2019072802000168.html
[15] ユリという植物は発芽に種子を必要としない
【参考文献】
・現代思想2019年11月号 反出生主義を考える——「生まれてこないほうが良かった」という思想 (加藤修一ほか 2019 青土社)
・Better Never to Have Been the Harm of Coming into Exitance (David Benatar 2006)
→生まれてこないほうが良かった——存在してしまうことの害悪 (小島和男・田村宜義訳 2017 すずさわ書店)
・夏物語 (川上未映子 2019 文藝春秋)
・性の歴史Ⅰ 知への意志 (ミシェル・フーコー/渡辺守章 訳 1976→1986 新潮社)
・自殺について 他四篇 (アルトゥール・ショーペンハウアー/斎藤信治訳 1851→1952 岩波書店)
・生誕の災厄 (エミール・シオラン/出口裕弘訳 1973→1985 紀伊國書店)
・日本仏教の社会倫理——「正法」理念から考える (島薗進 2013 岩波書店)
・全体主義の起源Ⅰ (ハンナ・アーレント/大久保和郎ほか訳 1953→1974 みすず書房)
・ 責任という原理:科学技術文明のための倫理学の試み (ハンナ・ヨナス/加藤尚武訳 1979→2000 東信堂)
・開かれた社会とその敵 (カール・ポパー/内田詔夫ほか 1945→1980 未來社)