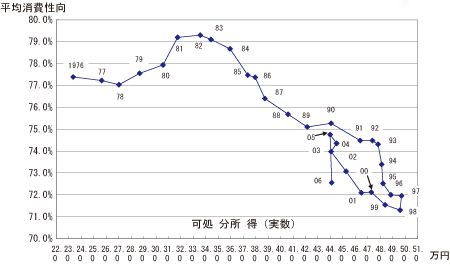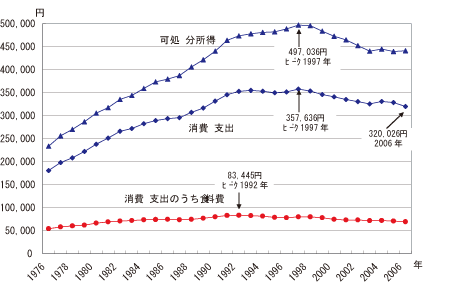入門!マクロ経済学!
GDPとは何か?―マクロ経済における指標
Ⅰ生産面から見たGDP
〇国民経済計算(SNA System of National Accounts)……一定期間にどれほどの経済活動が行われたかで、一国の経済力を測る指標。
→しかしここでは各財・サービスの材料費などが重複して含まれてしまう(二重計算の問題)。例えばコンピューターを一つの財とした場合、その中の電子部品の産出費も国民経済計算に計上されてしまう。
〇二重計算の問題は、財・サービスの生産費から原材料等=中間生産物の額を差し引いた粗付加価値のみを合算することで解消される。
→ある期間中における財・サービスの粗付加価値を、市場価格で評価し、生産全体で合計した金額を国内総生産(GDP Gross Domestic Product)と呼ぶ。
〇またGDPは最終生産物の生産額を合算することでも算出できる。先の例ならば電子部品は中間生産物、コンピューターは最終生産物となる。
〇国内純生産(NDP Net Domestic Product)……GDPから固定資本減耗を指しい引いた金額。統計上はGDPより正確な指標だが、減価償却を厳密に計算することは困難であるため、一般的にGDPと併用される。
Ⅱ分配から見たGDP
〇生産活動は、生産に参加した経済主体に対する分配の観点からも把握できる。例えば労働賃金や、土地や資本の賃貸料や利子などがそれである。
→このような生産活動によって得られた所得を要素所得と呼ぶ。
〇要素所得は[a]雇用者報酬と[b]営業余剰・混合所得から構成される。
[a]雇用者報酬……労働に対する賃金や俸給
[b]営業余剰・混合所得……法人企業の得る利子や賃貸料(個人企業の場合、混合所得)
→したがって、GDP=雇用者報酬+営業余剰・混合所得
+(生産・輸入に課される税-補助金)
+固定資本減耗
〇一方、分配された総生産は支出の面からも捉えられる。これが国内総支出(GDE Gross Domestic Expenditure)である。
〇以上のことから、総生産=総所得=総支出という等式が成立する。
→これを三面等価の原則と呼ぶ。
ⅢGDPの範囲
〇以下ではGDPに含まれるもの・含まれないものを検討する。
[a]市場価格で評価できない労働……含まれない
→専業主婦による家事労働は市場で取引されるわけではないためGDPに含まれない。
[b]市場で取引されないが、生産物に含まれるもの……含まれる
→官公庁の窓口など、政府の行政サービスは市場で取引されていないにもかかわらず、そのサービスを提供するうえでかかった費用(人件費など)はGDPに含まれる
[c]市場で取引されないが、GDPに含まれるもの
→農家の自家消費、会社員の現物給与、持ち家のサービスなどは市場で取引されないが、財として認められるためGDPに計上される。この時、帰属価格という価格を当てはめて産出する(例えば無料社宅は家賃に換算すると○○円など)
Ⅳ国内/国民の区別
〇GDPを産出するうえで、国内/国民の区別は重要である。
国内……地理的領土に基づく境界
国民……1年以上国内に居住している者
→GDPは一定期間における国内の生産額の合計だった。したがって出稼ぎ労働者などの外国人による生産活動も含まれることになる。
〇一方で、居住者という意味での国民が一定期間に行った生産活動の所得の合計は、国民総所得(GNI Gross National Income)として定義される。ここには外国人による国内での所得は含まれないが/日本人による国外での所得が含まれる。
→したがって GNI=GDP+海外からの所得-海外への所得 という関係が成り立つ。
〇「一国の豊かさ」の指標としてはGNIが適切であるといえる。
Ⅴ名目値と実質値
〇GDPを一定期間における単に財の粗付加価値の総計とした際、評価はその期間における市場価格によって決定される。これを名目GDPと呼ぶ。
→しかし物価上昇などの価格変動も含むことになるため、純粋な生産活動の指標としては不適切である(日本の2000年のGDPは1960年のそれと比べ30倍以上も成長していることになってしまう)。
〇そこで、ある年を基準年として固定し、その年の価格水準ですべての年のGDPを再評価する方法が取られる。このように算出されたGDPを実質GDPと呼ぶ。
[ex]基準年より価格が上昇した場合、名目GDPは増えることになるが/各生産量の値が同一のままなら、実質GDPは変化しないことになる。
〇名目GDP/実質GDPの値をGDPデフレーターと呼ぶ。
→先述の通り、実質GDPは生産量が変化しないかぎり不変であるため、GDPデフレーターの値が上昇する/減少する=名目GDPの値が変化する=価格変動の指標となる。
〇例えば90年代以降の日本では実質GDPが上昇している/名目GDPが下落する=GDPデフレーターが低下している状況が観察される。したがって物価が下がるデフレが起こっていると結論付けられる。
消費と貯蓄の理論
Ⅰケインズの理論
〇消費関数……マクロ経済全体における消費量の決定を分析する
→最もオーソドックスなものがジョン・メイナード・ケインズによるケインズ型消費関数
【ケインズ型消費関数】
[a]基本理念……「消費は現在の所得水準に依存する」
Yd——可処分所得=現在の所得から所得税を差し引いた所得(自由に使える所得)と定義
C——消費量
A——基礎消費=可処分所得が0でも支出される消費(食費など)
c——限界消費性向=Ydが限界的に1円増えたとき、消費がc円増えることを表す
(限界消費性向は原則的に0<c<1。可処分所得のすべてが消費に回されるわけではない/貯蓄にも振り向けられる)
とすると、[a]より消費量CはYdに依存するので、
C=A+cYd
※切片となる基礎消費Aはグラフ上でb
〇消費線(C=cYd+A)の傾きは限界消費性向(0<c<1なので45°以下の角度)
〇C/Yd——平均消費性向=可処分所得のうちどれだけ消費にあてがったかの平均
→原点Oと各点を結ぶ直線の傾きとなる
→ケインズの理論において、平均消費性向は可処分所得が増加するにつれ減少する
〇また貯蓄をSとすれば、S=Yd(可処分所得)-C(消費)なので、SとYdの間には、
S=(1-c)Yd-A
という関係が成立する。
→(1-c)は限界貯蓄性向=Ydが1円増えたときに、貯蓄がc円増えることを表す。
Ⅱケインズ理論の説得性
〇ケインズの説得性を明らかにするためには、我が国における実際上の統計データに照合してみる必要がある。
→統計データは以下の2種が主である
①クロスセッション・データ……特定の年に、さまざまな可処分所得をもつ家計が、どれだけ消費を行ったか示すデータ
②時系列データ……時間を通じて可処分所得が変化していくにつれて、消費がどのように変化したか示すデータ
【①クロスセッション・データ】
※グラフは2008年のもの
〇クロスセッション・データには、日本では総務省の「家計調査」が相当する。
→収入階級が高くなる=可処分所得が増加するにつれて、平均消費性向が減少していく傾向が観察される。
〇これはケインズの「可処分所得と平均消費性向の反比例」という仮説を支持する。
【②時系列データ】
〇グラフを見れば明らかなように、1976年~2006年までの30年間で、可処分所得の増加と平均消費性向はほぼ比例している。
→したがって、長期の消費関数と、ケインズの「可処分所得と平均消費性向が反比例する」という仮説は合致しない(ケインズの理論上は、可処分所得が増加するならば、平均消費性向は減少する必要がある)。
〇しかし短期的に見れば、消費関数の傾きは長期間数のそれよりも小さいため、ケインズの理論が合致する。
→クズネッツがアメリカの2次大戦以前のデータを用いて、この長期と短期の矛盾する性質を明らかにした。
Ⅲケインズ型消費関数への反駁
〇ここではケインズの理論への反駁として、①ライフサイクル仮説と②恒常所得仮説の2つについて検討する。
①ライフサイクル仮説
〇限界効用……限界的に財が1単位増えるに従い、増加する効用n。消費量が小さければ大きく、消費量が大きければ小さくなる(ただし限界効用は逓減する)。
→Ydが多い時期には貯蓄し、少ない時期に消費には回す消費パターンが合理的である=c(限界消費性向)はYdに比例して増加するというケインズの理論と違背する事実。
〇モディリアーニと安藤によって提唱されたライフサイクル仮説は、このような消費パターンの合理的平準化に注目するものであり、人々の消費は期間ごとの可処分所得ではなくて、その個人が一生涯を通して獲得することのできる可処分所得の総計、すなわち生涯所得によって決定されるとした。
〇図のように最も稼げる時期には貯蓄に回す傾向が強くなり/逆に稼げない時期(入社時期と退職後の貯金を切り崩す時期)には消費に多く支出して限界効用を増加させる。
②恒常所得仮説
〇フリードマンもまた消費が一期間の可処分所得ではなくて、時間を通じた平準化によるものである事実に注目する。
→ライフサイクル仮説と異なるのは、消費が生涯所得ではなく、生涯所得の平均値=恒常所得によって左右されるものであるとする点である。
〇また一時的な収入(ギャンブルに勝利、土地の売却、宝くじに当選など)は恒常所得に対して変動所得と呼ばれる。
→毎期の得られる可処分所得Ydは、恒常所得Ypと変動所得Yrによってあらわせるので、
Yd=Yp+Yr
〇そして消費Cは恒常所得のみに依存するので、
C=kYd
となる。このとき変動所得は主に貯蓄に回されると考えられる。
乗数理論
Ⅰ ケインズ学派の登場
〇古典派は経済の自動調節機能に着目したが、1929年10月24日(「暗黒の木曜日」)に端を発する世界大恐慌によって、従来的な経済学の理論が通用しない未曽有の不況を経験することになる。
→そこで登場したのがマクロ経済学の父祖であるケインズであり、放任経済路線から政府の市場への積極介入を促す理論が確立されることになる。
〇古典派において、一国の総生産量は供給能力によって規定されており、実質国民所得は総供給のみによって決定されるとされてきた(セイの法則)。
→これに対しケインズは国民所得が低迷し、高い失業率が発生するのは、総需要の低迷が原因であるとし、特にこれを有効需要と呼んだ。したがって有効需要の増加が失業や遊休設備解消に繋がることになる(有効需要の原理)。
〇今日的には多くの異論が寄せられているが、一般にケインズの主張は価格が硬直的な短期経済を説明するものと受容され、乗数理論やIS-LM分析などもそうした解釈の中の産物である。
[古典派/ケインズの差異]
〇古典派/総供給が総生産を決定する……仮に超過供給が発生すれば、市場の自動調節機能によって、需要に合わせて価格が下落する。逆に需要が過多となれば、供給量が今度は増加する。
〇ケインズ……価格が硬直的な場合、上述のような供給/需要の増減によって価格は変化しない。その結果、企業は財・サービスの数量調整を行うことになり、解雇や雇用によってこれを変動させる。
〇有効需要の拡大には以下のような政府介入があり得る。
①財政政策……政府支出や租税を裁量的に変化させ、国民所得をコントロールする。拡張路線/緊縮路線など。
②金融政策……貨幣供給量や利子率を変化させ、景気を変動させる。量的/質的金融緩和が代表的。
Ⅱ 有効需要の原理
〇政府支出をG、財市場の総需要をD、民間消費をC、民間投資をIとし、この間に海外との取引がないと想定すると、
D=C+I+G
〇つまり一国の財・サービスに対する有効需要は、家計の消費支出(C)や住宅投資(I)、企業の投資(I)、あるいは政府支出(G)の合計によって発生する。
〇すでに見た通り、所得から租税を引いた額が可処分所得である。そしてケインズの消費関数においては、消費は民間の可処分所得に依存して次のように決定される(Cが総消費、cは限界消費性向、Aは基礎消費、Yが所得、Tは租税)。
C=A+c(Y-T) ただし,0<c<1
→これを先の有効需要の式に代入すると、
D={ A+c(Y-T)}+I+G
〇またケインズの有効需要の原理では、総需要が総生産を決定されると仮定されているため、総生産Yは常に有効需要に等しい。したがって総生産に等しい国民所得Yは、
Y={ A+c(Y-T)}+I+G
→上式を満たす国民所得の水準は均衡国民所得と呼ばれる。この式が成立する限り、財市場が均衡しているためである。
Ⅲ 乗数理論
〇ケインズによって定式化された乗数効果は、今日では様々な種類がある。
①政府乗数効果
〇まず前提として、先の通り価格が硬直的な市場において、有効需要の増加は均衡国民所得の増加を意味する(有効需要D=総所得Yなので比例して増加)。
〇ΔGを政府支出の増加上方率とすると
[a]第一ラウンドとして、有効需要ΔG分の増加、
[b]第二ラウンドとして、政府支出ΔGによる有効需要の増加分の国民所得の増加分(DとYは比例)ΔG×限界消費性向c分の増加=cΔG
[c]第三ラウンドとして、さらにcΔGによる有効需要増加分の国民所得増加分c²ΔGが加わる(以下同様)
〇無限等比数列なので収束し、最終的には
1ΔG/1-c
が増加することになる。
②租税乗数効果
〇逆に租税Tを引き上げれば、そのぶん所得Y=有効需要は下がる。したがって政府乗数効果と逆に、
1ΔG/1-c
が最終的な有効需要と総所得の減少分である。